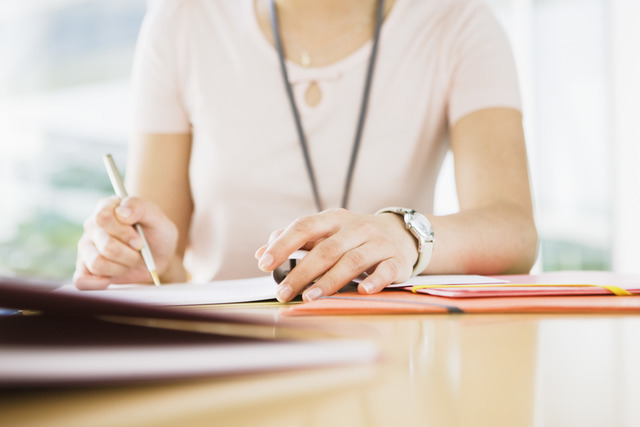すぐに、退職・転職を考えてしまう「あなた」のためのカウンセリング!
心理カウンセリング/トラウマ治療(神奈川県横浜市)
IAP横浜相談室
【主な実施場所】(関内駅周辺の施設に変更になる場合があります)
〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目4-7 澤田聖徳ビル
コラム「とらわれからの解放」
代表カウンセラーコラム過去記事1
Web上アディクションセミナー
第2講 依存症・アディクションとは何か
(令和3年1月17日)
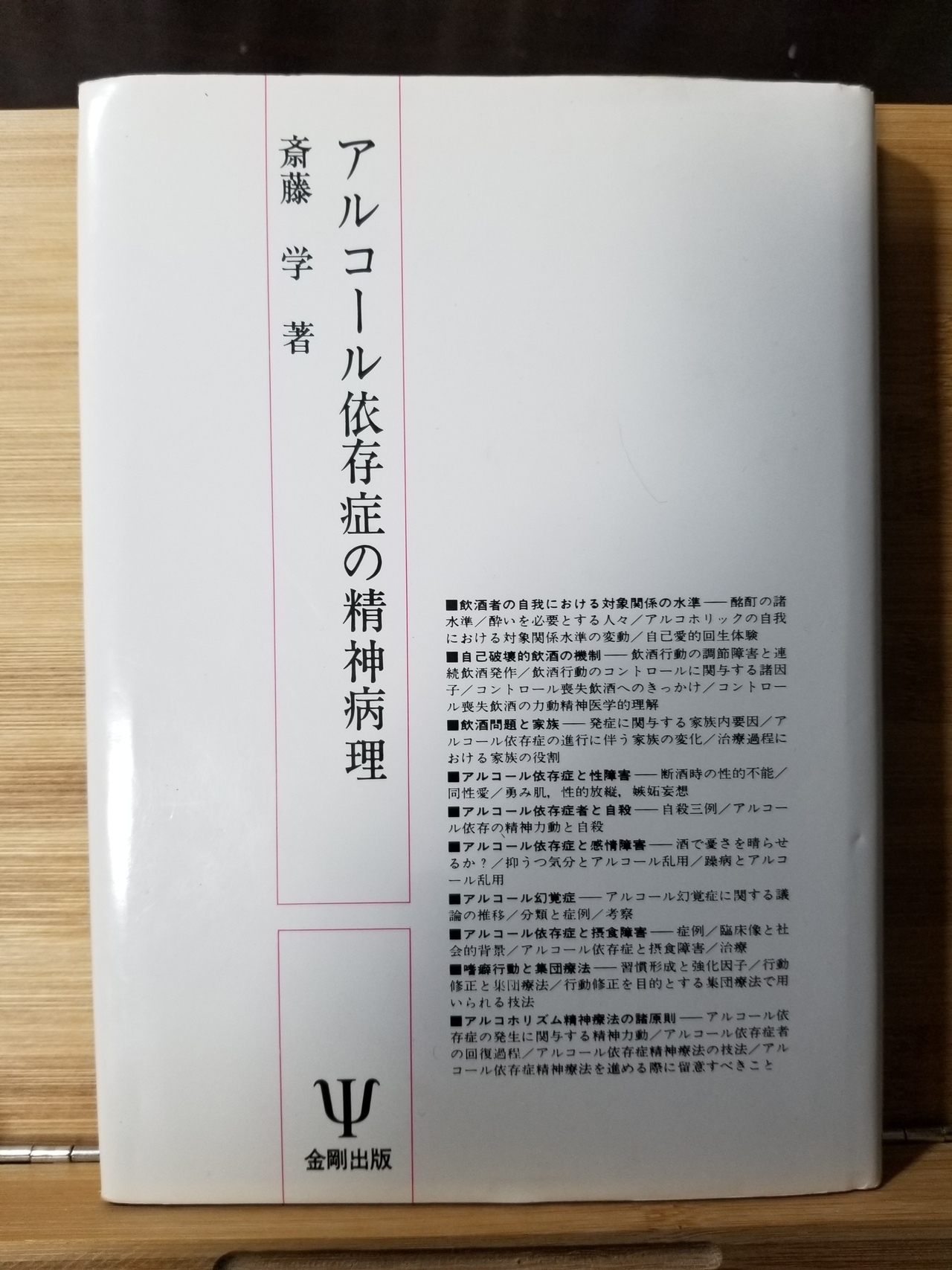
「アルコール依存症の精神病理」斎藤学 著
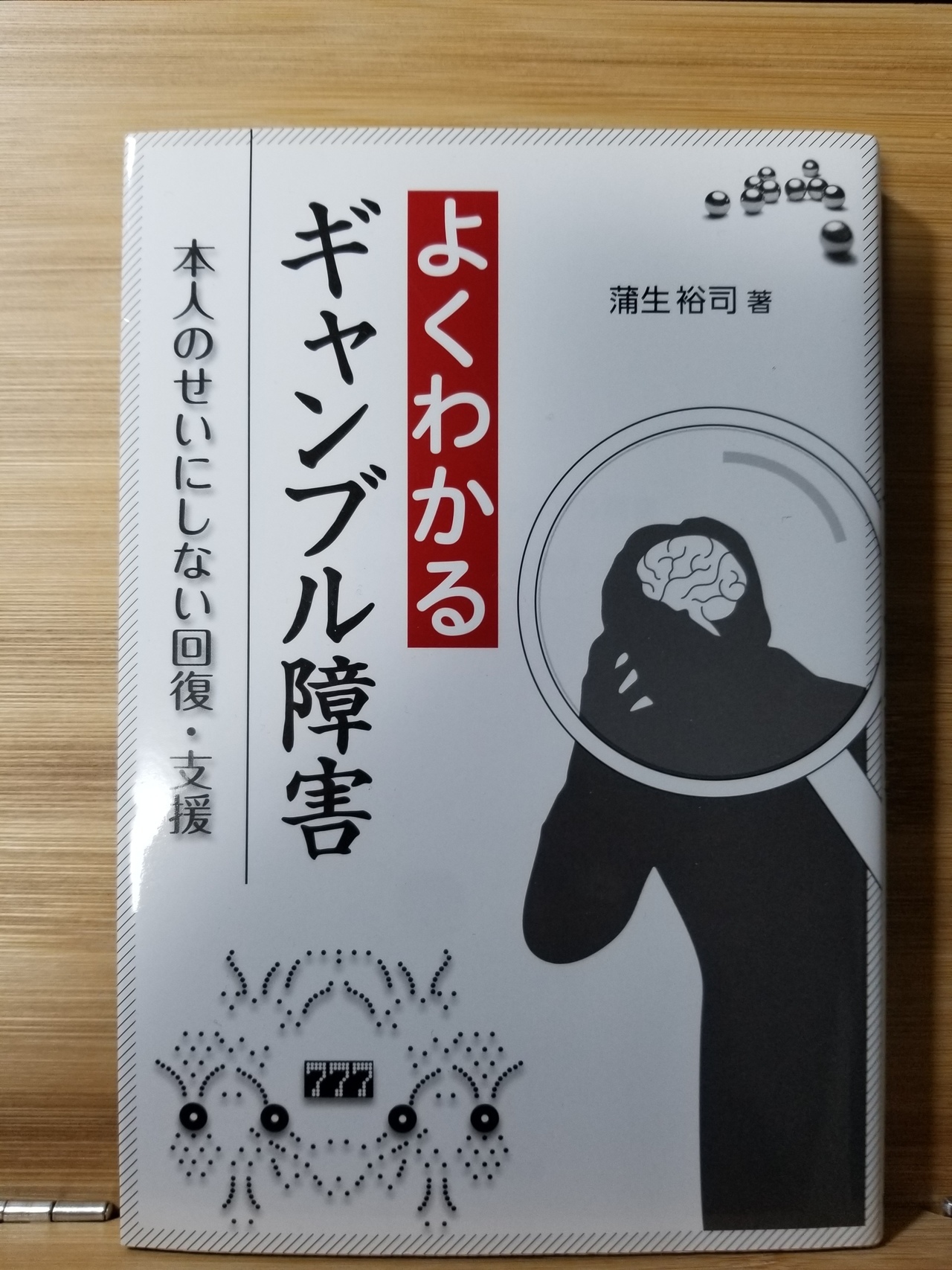
「よくわかるギャンブル障害」蒲生裕司 著
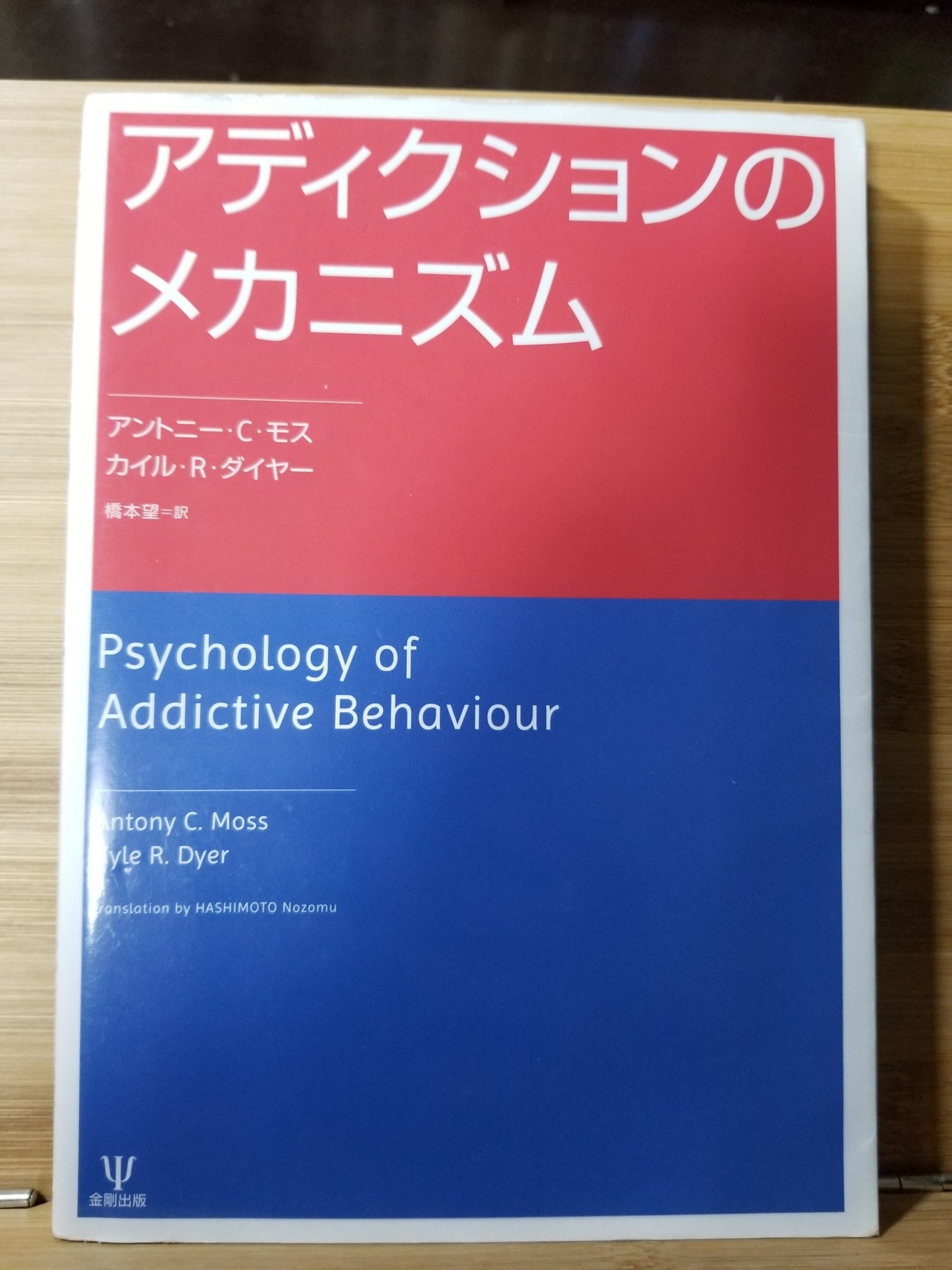
「アディクションのメカニズム」アントニー・C・モス、カイル・R・ダイナー 著
目次
1,依存症治療のはじまり
薬物依存に関する医学的研究は、18世紀後半のアルコール関連疾患(飲酒による栄養素低下による多発性神経炎や・アルコール性せん妄など)に始まり、内科医が担当していました。
19世紀半ばにフランスのフスという内科医からアルコホリズム(飲酒に問題がある状態)という言葉が使われ、フランスの精神科医マニャンがアルコール性精神症状の研究を進展させました。その研究はクレペリンの中毒性精神病の概念に統合され、精神医療の中で薬物依存とのかかわりが始まったのです。
その際、体外からの毒の摂取による大脳の反応のみが注目され、人と状況が取り落とされた「脳病理学的モデル」が長く精神科医の関心となっていっていました。そして、ヒトー薬剤―環境(状況)の均衡関係を取り上げた「疫学的生態学的モデル」が薬理学領域からシーヴァースらによって提出され、これは現在の薬物依存概念に繋がるものでした。
薬物依存の臨床的問題は①精神依存②身体依存③慢性中毒④急性中毒です。研究において精神依存については見逃されることが多かったのですが、ジェネリックにより精神依存を中心とした、精神病理学にまとめられました。こういった視点の移り変わりの中で呼称も「慢性アルコール中毒」から「アルコール依存症」へと変化していきます。
依存と依存症は区別して考える必要があります。晩酌飲酒者のように、健康な飲酒者の中にも厳密にいえばアルコール依存は存在します。飲酒行動を異常と捉えるかどうかは社会・文化によって違ってきます。毎日、晩酌をしながらコントロールして飲酒を楽しめていれば依存症ではないですが、コントロールを失い、生活に支障が出たものは依存症として医療の対象になると考えられます。
2,依存症・アディクションにまつわる言葉の整理
依存と依存症との違い、それらとアディクションとの違いは一体何なのか、第1講で少し述べましたが分かりづらいです。これらにまつわる用語の整理の中で少しずつ理解を共有していきたいと思います。アルコールを中心に中毒、乱用、依存、嗜癖(アディクション)という言葉を見ていきましょう。
中毒とは、「摂取した薬物の薬理作用による異常な状態」とされています。お酒を飲んで酔っ払い、人に迷惑がかかるような行動をしたり、吐き気が強くなりひどいときには嘔吐してしまったり、挙句のあてに意識を失ってしまうような状態です。このような状態を急性中毒と呼びます。
アルコール中毒とアルコール依存症は別のものですが、アルコール中毒を略して「アル中」と呼び、アルコール依存症になってしまった方の蔑称として使われる風潮がありました。差別的な言葉の使い方であり、改めるべきかと思います。
また、慢性中毒と呼ばれているものは、お酒の飲み過ぎで肝硬変などの肝臓障害になったり、長期的にお酒を飲むことによる身体が不健康になっていったりすること全般をさします。
乱用とは、「社会的許容範囲から逸脱した方法。目的で使用すること」と定義されています。これは文化的な背景よって左右されます。同じ薬物でも合法とされる国と違法である国があります。同じ人が同じように薬物を摂取しても一方では犯罪になりますが、他方では特にお咎めがないといったこともあるのです。同じ日本でも、一般のサラリーマンが仕事中に飲酒をしていれば、乱用と見なされることが多いと思いますが、仕事が終わったアフターファイブに飲み屋でお酒を飲んでいても乱用とはみなされないことでしょう。
また、児童虐待を英語では「Child Abuse」といいます。Abuseとは乱用という意味です。子どもと不適切に関わっているという意味に捉えることもできると思います。乱用を繰り返すと依存になることから、家庭内の様々な暴力も依存・アディクションと捉えることもあります。
依存には身体依存と精神依存があります。
身体依存とは「薬物の血中濃度が低下すると、さまざまな症状が出てくる状態」とされています。身体から、薬物が抜けると出てくる症状のことを離脱症状といいます(以前は禁断症状と呼ばれていたこともありました)。汗をかいたり、手が震えたり、眠れなくなったり、興奮状態や幻覚が生じ、自分がだれで、いつ、どこにいるのかわからなくなる見当識障害が生じることもあります。
精神依存とは、「薬物の血中濃度が低下すると、その薬物を再使用する渇望が強く出現する状態」です。精神依存が強くなると生活の中で薬物を探し摂取することが、最優先事項になっていきます。依存症はよく「わかっていてもやめられない」状態と言われます。依存症・アディクションの中核的な症状は精神依存によるコントロールの喪失であるといえるでしょう。
アルコールという薬物の摂取による身体的・精神的な反応を見てきましたが、薬物を摂取していなくても、コントロールの喪失が生じる、「ギャンブル依存」、「摂食障害」、「買い物依存」、「仕事依存」、「恋愛依存」、「セックス依存」、「自傷行為」などをどのように捉えればよいのでしょうか。
蒲生は、「依存症という表現がアルコールを含めた薬物の薬理作用にも基づく表現」として、薬物が関わっていないものは医学的には依存症という表現は適切ではなく、嗜癖(アディクション)、嗜癖障害という表現が使われている、としています。
私は、さまざまなメカニズムの中でコントロールを失ってのめりこんでしまう状態を広くアディクションと捉え、それが原因で社会生活・日常生活に支障が出ているものを依存症として医療・治療の対象として考えていきたいと思います。
しかし、2013年に改訂されたDSM-5(「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版」アメリカ精神医学会)では依存症という言葉は使われておらず、「物質関連障害および嗜癖性障害群」というカテゴリーの中で、アルコール関連障害として「アルコール使用障害」、非物質関連障害として「ギャンブル障害」などと表現されているので、厳密な言葉の使い分けは難しいようです。
〈参考文献
・「人はなぜ依存症になるのか 自己治療としてのアディクション」エドワード・J・カンツィアン マーク・J・アルバニーズ 著 松本俊彦 訳 星和書店 2013年5月発行
・「トラウマの臨床心理学」西澤哲 著 金剛出版 1999年2月発行
・「よくわかるギャンブル障害」蒲生裕司 著 星和書店 2017年9月発行
Web上アディクションセミナー 第1講 はじめに(令和2年12月29日)
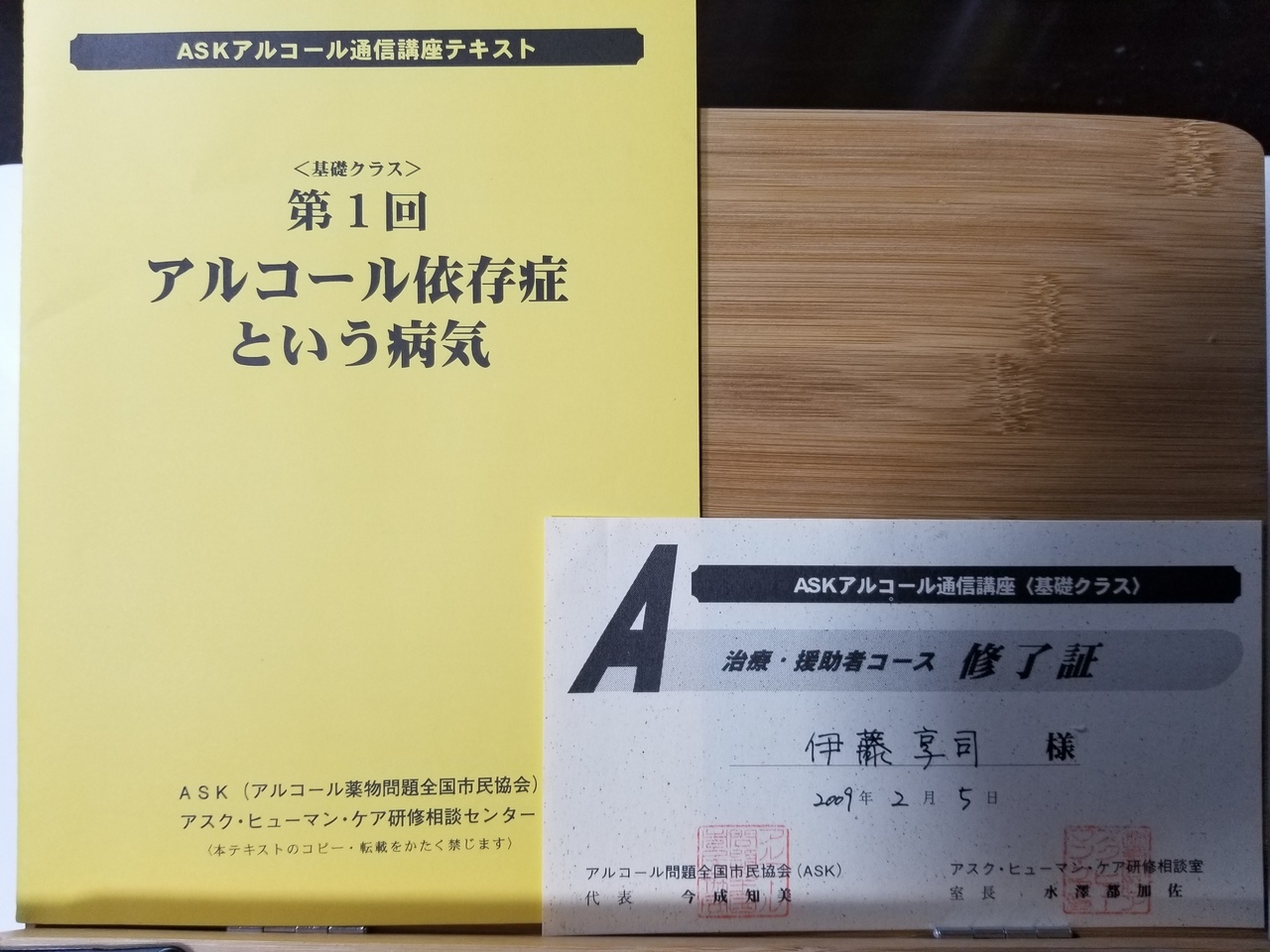
依存症について学んだ「ASKアルコール通信講座」のテキストと修了証。編集 ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)
発行 (株)アスク・ヒューマン・ケア
アディクションとは、ある習慣に「不健康にのめりこんだ・はまった・とらわれた」状態であり、社会生活・日常生活に支障をきたしている状態を依存症としています。アルコール依存症・薬物依存症がモデルになっています。その他でも「ギャンブル依存」、「摂食障害」、「買い物依存」、「仕事依存」、「恋愛依存」、「セックス依存」、「自傷行為」などがアディクションと捉えられています。(アスク・ヒューマン・ケアホームぺージより一部引用)
アディクションは思っているより私たちの身近にあるものです。トラウマ等大きなストレスによって生きづらさを感じ苦しいときに、アルコール、ゲーム、ネット、性的快感等を利用し紛らわせ、なんとか生き延びてきたという人は私だけではないと思います。
依存症という診断名がつくのは何らかの生きづらさから生じる症状のひとつであって、その根本は依存症以前にあると考えています。
依存症は病気なので治療が必要。それはその通りなのですが、生物学を基盤とした医療だけでは依存症は治すことが出来ません。抗酒剤で恐怖によってアルコール摂取を止めるぐらいなのです。恐怖によって依存は回復できないというエビデンスがヨーロッパにあるんですね。それ以外はうつや不安など精神症状に薬を処方する程度で、一般の精神科医療と何も変わらないのです。
依存症専門病院がやっていることは、依存症であるという心理教育とセルフヘルプ的なグループセラピー、家族に対する支援です。
心理教育に関しては、通常ではない脳の状態を理解しないといけないので、そこは専門の医師が必要でしょう。しかし、そのうえで、どのような時に依存対象に手を出してしまうのか、どのような対応が必要なのかという点は、依存症の人に限らず生きづらさを抱えている人皆に必要な情報だと思います。
グループセラピーに関しては、多くがAA等のアノニマスグループで行われている「言いっぱなし、聞きっぱなし」の形をとったグループが主流です。アノニマスグループは依存症だけでなく、アダルトチルドレンのグループ、感情に関してのグループなど、さまざまなグループが生まれており、依存症に限ったことではありません。
また、近年依存症へのアプローチとして誕生した動機づけ面接も依存症に対してのみ特別に有効という訳ではなく、人が良い方向へ向かうこと全般に有効なものです。
依存症という病気に医療機関が、まず対応したことから専門医療が必要と言われますが、実は一人一人の生きづらさを軽減し少しでも生きやすい生き方を身に着ける。それが依存症治療の中心であって、すべての生きづらさを抱えた人に必要なことなのです。
医療が必要ではないということではなく、身体のケアとして必要なことは医療が必要だけれども、必ずしも依存症専門である必要はないだろうという考えです。
トラウマ・生きづらさを専門にカウンセリングを行っている当相談室ではそういった視点で依存症・アディクションをとらえています。
なので、ここで皆さんとアディクションというものを共通理解することは、これからトラウマ・生きづらさからの回復活動をはじめる私達には有益なことだと思いました。これがコラムでアディクションセミナーをはじめる理由なのです。
孤立と先端(令和2年10月21日)
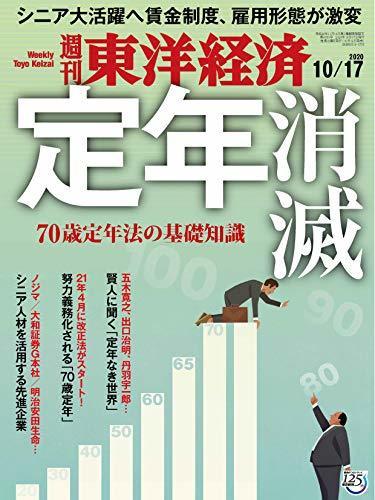
ぺらぺらめくっていた週刊東洋経済10月17日号
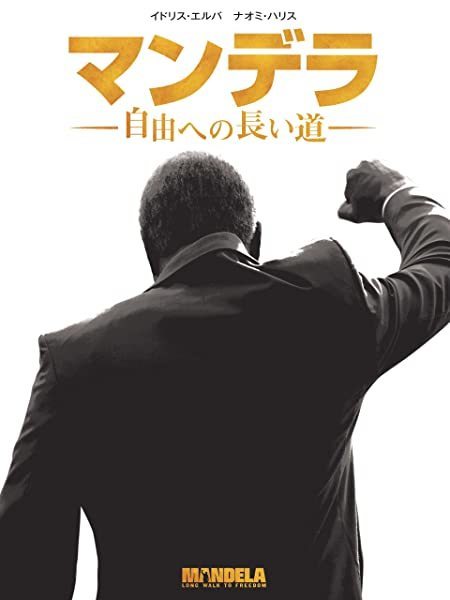
私が観た映画「マンデラ-自由への長い道-」

これから読む「ネルソンマンデラ私自身との対話」(明石書店)
週刊東洋経済10月17日号の解説欄を見ていました。今号のテーマは定年消滅だったのですが、解説欄では前号のテーマ〈テスラ〉についてでした。
テスラとは電気自動車で注目されているメーカーです。テスラの最高経営責任者であるイーロン・マスクについても前号で特集されていたのですが、今号の解説欄ではそのイーロン・マスクが尊敬して、会社の名前の由来にもなった<二コラ・テスラ>について言及していました。
「1世紀前のこの天才は、交流電流システムの発明と事業化という輝かしい業績を上げた。だが、『世界システム』と称した地球規模の無線送電事業には成功せず、晩年は失意と孤立の中にあったという。一方で異端は『認められると先端になる』と前向きにも捉えられる。」
一部切り取って引用しましたが、天才は孤立してしまう、ということは結構言われていることだと思われますし、それが認められた時に大きな成果を出すということも、多くの人がなんとなく察していることかと思います。
私がこの文章に触発されたのは、まさに今私自身が孤立感を強く感じているからですが、私の中に〈先端〉があるとも全く思えないなーと思ったのです。
インサイトカウンセリング株式会社に私のカウンセリングのスーパーバイズをお願いしていますが、その代表の大嶋信頼先生は孤立と天才の人だと思います(ブログを読むとこの人も結構やばかったんだって分かりますね)。学会や偉い先生・権威に認められたのではなく、クライエントをはじめ、著書の読者など一般の人に認められて先端になった人だと思います。
ここで私の孤立を見つめてみます。一つのトラウマ被害から身近な人間関係・住み慣れた地域を失い、孤立して生きていかなければいけない〈失意〉を持たざるを得なくなります。なので、私の中にあるのは孤立せず、人とつながることのできるコミュニティの創造なのです。それは、まぁ、やればいいんですけど。何か前に進めない…。
話は変わりますが、私が尊敬している偉人の中にネルソン・マンデラがいます。南アフリカ共和国初の黒人大統領になった人です。アパルトヘイトという白人政府による徹底した黒人差別政策があり、それと戦い解放に導きました。
マンデラの場合、アパルトヘイトという巨悪と戦ったのではないかと思います。しかし、私の場合、やれば良いことをやるだけなのに前に進めない、特に敵はいないのです。
では私を孤立させ、動かせなくさせるのは一体何なんでしょう。おそらく、私の中にいるのです。巨悪は私の中に住んでいて、私は私の巨悪と戦って勝たなければいけない。そのためにインサイトカウンセリングに通い続けたし、今もクライエントのケースを通して私自身が私の巨悪と戦っているのだと思います。
最も、マンデラ自身も自分の中での戦い、葛藤も相当あったそうです。実は、私は「マンデラ」という映画一本しか見ていないのですが、マンデラ自身の著書のなかには、人間としての葛藤が描かれているそうです(「ネルソン・マンデラ 私自身との対話」明石書店)。これからすぐに、Amazonで買います!(笑)。
スーパーバイザーの泉先生がスーパーバイズの中で「クライエントと共に」「クライエントから教えていただく」という姿勢を何回も強調されます。もちろん、私がカウンセラーとして成長するためですが、巨悪に打ち勝つように導いていただいているものと思っています。
東洋経済をペラペラめくっていながら、想ったことを書いてみました。テスラのイーロン・マスク氏やネルソンマンデラ、大嶋信頼先生と並べて自分の事を書くのは何ともおこがましいとここにきて思いましたが、いまさら、文章を変えられませんし、お蔵入りにさせるのももったいないので、このまま投稿させていただきます。と書きながら、心の中では私達、普通に苦しんでいる人間もじつはこのようなすごい人たちとそんなに変わらないのではないか、と思っている自分がいます(笑)。
最後に、私は個人の回復、成長、尊重がもっとも大切だと思っています。政治・経済・社会保障・安全保障について知り・考え・行動することが、それを実現するために必要ではないか、少し深く知りたいなと思い週刊東洋経済を読んでいます。
子育て・教育について(令和2年8月6日)
前回の更新から、一年弱が過ぎてしまいました。その間に相談室の移転もあり、コロナ騒動が始まりコラムが後回しになってしまいました。「諦めなければ、それは失敗ではない。」誰かがそんなことを言っていたような気がします。
コラムの発信は私とって大切なこと。ネットで日本中、世界中の人に私の考えた事、感じた事を伝えることが出来る。
様々な状況の中で中断してしまいましたが、諦めずにコラムの更新をを続けたいと思います。
今回のテーマは、子育てと教育について。以前にも少し書きましたが、大学入学は、子どもの問題、特に思春期・青年期の精神保健に興味を持っていました。
私の中で、「心の問題は大きいと思うが、その人に起きていることを個人の心の問題に還元してはいけないのではないか、家庭や学校、社会全体の問題で、しっかりと社会が対応していかないといけない問題なのではないか。」と考え。心理学ではなく、社会福祉を専攻することにしたのです。
とはいっても、心の問題はやはり重要だと思い、特に家庭での子育て、学校を始めとして周囲の大人による教育は個人に大きな影響を与えると考えていました。、大学に入学したばかりの頃は、子育てや教育のあり方を1人でぐるぐる考えていました。以下、当時考えた事を想い出してまとめました。
人は生まれた時から生きる力、学ぶ力を持っており、生きようとするし、学ぼうとする。周りの大人は、それを邪魔しないことしかできない。その子が生きようとし、学ぼうとする。それに対する障壁を取り除くことのみが教育。
本人の課題を親等が勝手にクリアしてしまうと、本人が生きる力、学ぶ機会を失うので本人自身が課題をクリアする必要がある。
一方、適切な情報提供とチャレンジする機会は周りの大人がしっかりと提供する必要がある。
そのバランスをとり、見守り、本人が困り、必要があれば相談に乗り一緒に考えることぐらいしかできない。
教育の理想とはこういうものなのではないか?
と学生の頃に考えていました。
「変えようとしないこと」「変化を起こしやすい環境を作ること」対人関係療法の第一人者水島広子先生が基本姿勢として示しています。*「トラウマの現実に向き合う:ジャッジメントを手放すということ」創元こころの文庫
子育て、教育、カウンセリング、精神療法そしてソーシャルワークなどなど、人と関わる基本姿勢は共通しているのかもしれません。
無意識の考察③(令和元年9月29日)
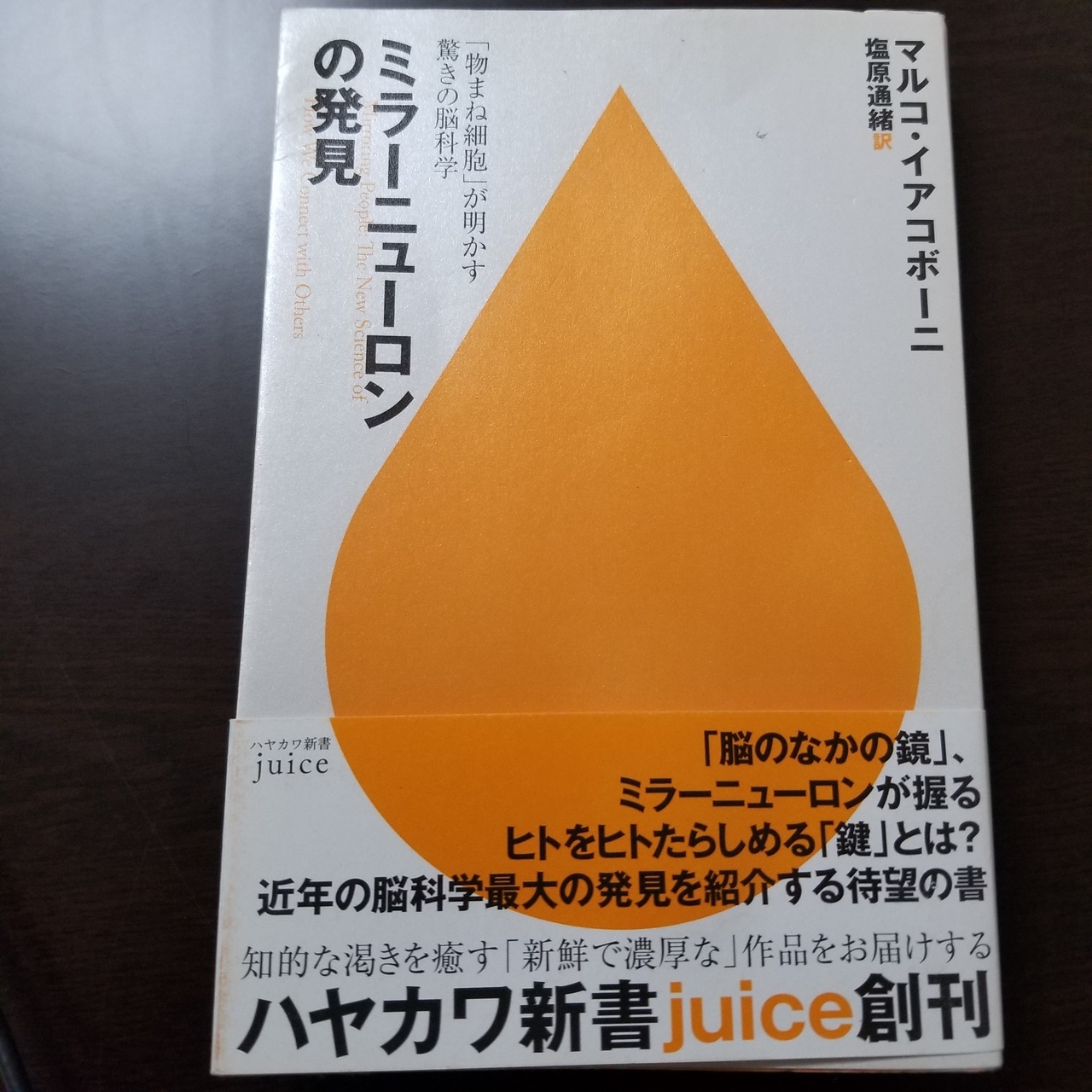
「ミラーニューロンの発見」マルコ・イアコポーニ(ハヤカワ新書)
大嶋信頼先生ががおっしゃっている「無意識」とは何か!第3弾です。今回は、「心に聴く」(詳細は「リミットレス」飛鳥新社を参照)の心とは何か私の仮説をお伝えします。
私の中で、目に見えない不思議な力というものをどうしても信じられない自分がいるのです。
なので、ふわーっとした「無意識」の話や、神様等、宗教の話を鵜呑みにすることが出来ません。人の生き方としては十分に参考にしていますが・・・。
しかし、「宇宙の自然法則」といった場合、「意識」でそれを理解することは出来ないが、それがそこに「ある」ということは心から納得できるのです。皆さまはいかがでしょうか。
ここで、「心に聴く」の話に変わりますが、「心よ」と唱えて、そのあとに答えてほしい質問を心の中で伝えると、心の声が聞こえます。
その「心の声」とは何なのだろう?何しろ「宇宙の自然法則」が存在するということはわかりますが、中身が分からないので、なぜ、「心の声」が聞こえるのかが分かりません。
しかし、私の中に1つの仮説があります。ある海外のテレビ番組でモーガン・フリーマンという黒人俳優が司会を務める「宇宙」をテーマにしたものを見たころがありました。
様々な学者が仮説を立て、それを立証するために最先端の研究をしていることを紹介してくれるものでした。
その中の一つに、ある物理学者が「宇宙に脳がある」と仮説を立てているのです。
宇宙に脳があり、思考している。その内容を理解するために、その物理学者はスーパーコンピューターを作成してします。
そのプログラムは完成したAというコンピューターより優れたBというコンピューターを作るという内容で、さらにBより優れたC、Cより優れたDを作るといった、より高度な性能のコンピューターを作っていくものです。
その結果、いつか宇宙の脳の処理速度と同じ処理速度のスーパーコンピューターが完成する。そうすれば、宇宙の脳が何を考えているのか理解できるのではないか、といった研究でした。
そのテレビを見て、私が考えたのは、宇宙に脳がある。ということは、ミラーニューロンもあるのではないか、では宇宙の脳と私たちの脳がミラーニューロンでつながってもおかしくないではないか、そこで私たちが分からないことを心に尋ねると、ミラーニューロンを通して宇宙が答えてくれている。
というのが、私の「心に聴く」の心の正体についての仮説です。
もっと短く分かりやすく表現出来たら、面白そうだなーって思います。最後まで、読んでくれてありがとうございます。