すぐに、退職・転職を考えてしまう「あなた」のためのカウンセリング!
心理カウンセリング/トラウマ治療(神奈川県横浜市)
IAP横浜相談室
【主な実施場所】(関内駅周辺の施設に変更になる場合があります)
〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目4-7 澤田聖徳ビル
コラム「とらわれからの解放」
代表カウンセラーコラム過去記事3
セリエのストレス学説を理解しよう!~無意識と一体になるために(令和元年7月29日)
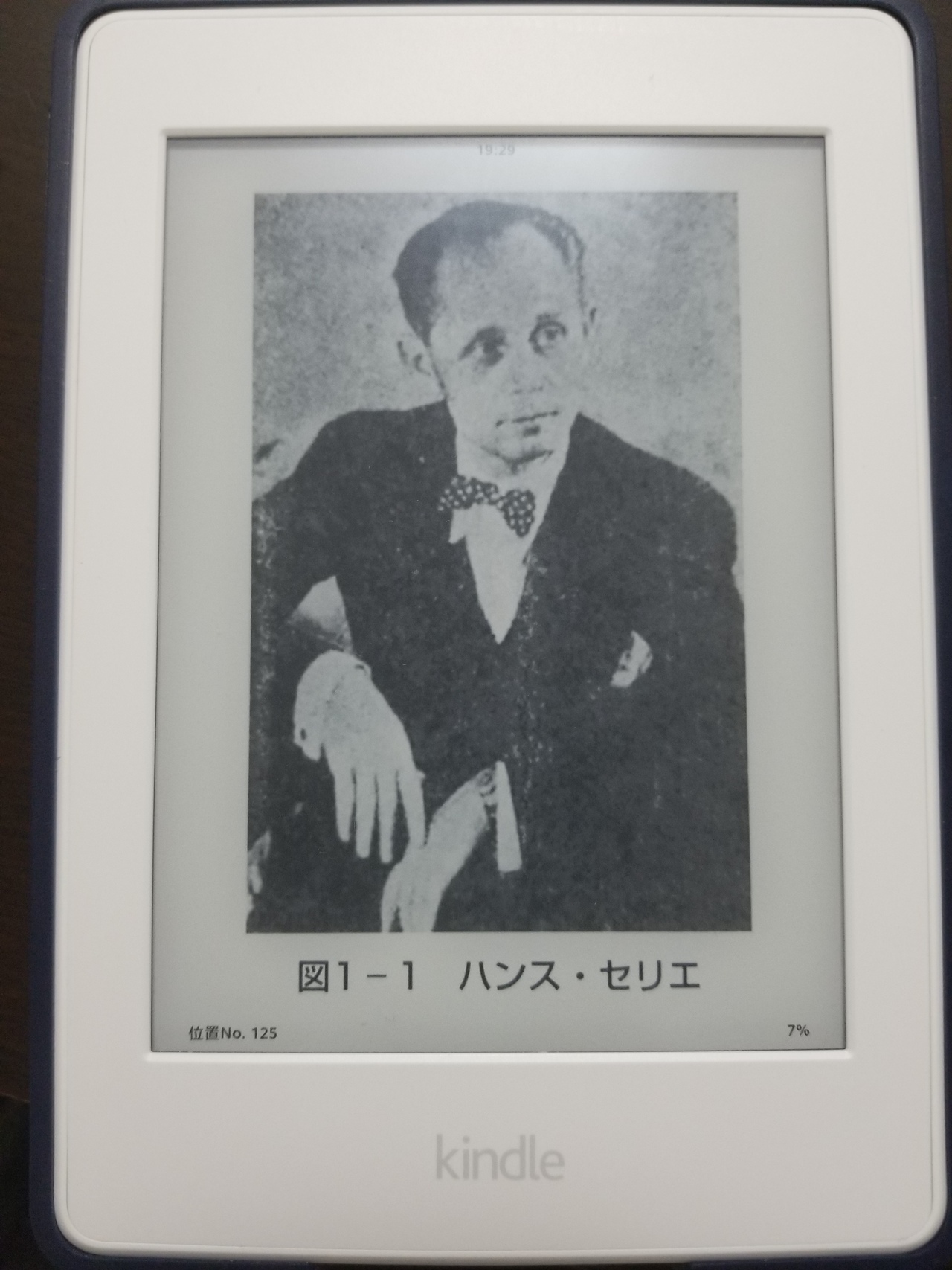
ハンス・セリエ
kindleで読みました(笑)
セリエのストレス学説について、「ストレスとはなんだろう 医学を革新した【ストレス学説】はいかにして誕生したか」(杉 晴夫著 講談社)を参考にしながらまとめました。
【目次】
・ストレス学説までの歴史
・セリエのストレス学説
・なぜ精神的ストレスが自律神経の失調を起こすのか
・まとめ
【ストレス学説までの歴史】
~ありふれた症状(非特異的症状)への注目~
1925年医学生だったハンス・セリエは臨床診断学の講義の中で「病人ならだれにでも見られるありふれた症状」に注目しました。それは、
・舌が白く荒れる
・発熱や胃腸障害
・やつれた様相
・体の痛み
等で、検査をすると脾臓や肝臓の肥大、扁桃腺の腫れ、皮膚の発疹が認められました。
しかし、当時は19世紀にはじまる細菌学の黄金期でした。それは感染症の特有の症状と感染症を引き起こす病原菌に対する対策を考えるのが順序であり、セリエが注目した「ありふれた症状(非特異的症状)」は病気の診断に役に立たないとされてしまいました。
それでも、セリエはその非特異的症状が体に現れるメカニズムを解明することが医学的に重要だと考えました。その考えがセリエの【ストレス学説】につながっていきました。
~先駆者たち~
ホルモンなどの内分泌学などセリエのストレス学説に大きく貢献した先輩研究者達の研究を紹介します。
・クロードベルナールとウォルター・B・キャノンの「ホメオスタシス」
外部の環境の変化に逆らって、体内の環境(内部環境)を一定に維持しようとする「ホメオスタシス」の機能を主張しました。
・高峰譲吉による副腎から「アドレナリン」というホルモンの発見。アドレナリンは止血作用があるとされていた。
・バンディングとマクラウドによるすい臓から分泌される「インシュリン」の発見。糖尿病の治療に活用されるようになります。
・バートラム・コリップの脳下垂体から「副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)」が分泌することの発見。これが【ストレス学説】で中心的な役割を果たす考え方になります。
~セリエの研究~
上述のコリップのもとで研究をしていたセリエは卵巣や胎盤から分泌する「性ホルモン」を見つける研究に参加しました。
卵巣や胎盤の抽出液をラットに注射すると起きる三つの反応
・副腎皮質の肥大
・リンパ組織の萎縮→抵抗力の減少
・胃腸の内壁の出血、潰瘍。
に注目しました。
それだけでなく、脳下垂体や腎臓、脾臓などのエキスでも三つの反応が起きました。
⇒エキスの中の不純物が変化や組織の損傷を起こすのではないか。
この3つの変化こそが医学生のときにセリエが注目した。「ありふれた症状」と共通するしくみがあるのではないかと考えた。
ラットを寒さや暑さにさらしたり、X線を照射したり、外傷を与える。出血・束縛させるなどの精神的恐怖を与えたり、過度の運動などの処置を与えると、どんな処置でも3つの変化が起こった。
⇒外部から加えられた「有害な作用」が何であろうといつも同じように反応すると考えた。
この考えをイギリス誌「ネイチャー誌」に投稿しました。当時この変化を「ストレス」と呼ぼうとしたが、すでに他の神経状態をイギリスではストレスと呼んでいたので「有害な原因」という言葉に置き換えられた。
【セリエのストレス学説】
・有害作用そのものを「ストレス」と呼ぼうとしたが、引き起こされる状態を「ストレス状態」と考え、状態を「ストレス」有害作用を「ストレッサー」と呼んだ
・ストレス反応を①警告反応期②抵抗期③疲はい期に分けた
① 警告反応期
・副腎皮質からグルチコイド(コルチゾールなど)が激しく分泌し、胸腺などリンパ系が萎縮。
・胃や腸の粘液が減少し、出血や潰瘍を起こす
② 抵抗期
・一度グルチコイドを出し切ってしまい放出が止まる。副腎が再び産生をはじめる。
・グルチコイドによって萎縮していた胸腺などのリンパ系が回復し体の抵抗力が回復。
・自律神経が回復し粘液が分泌、胃腸の出血や潰瘍も見られなくなる。
③ 疲はい期
・グルチコイドにより栄養素からストレスに抵抗するエネルギーを作っていたが、エネルギーには限度があり、再び副腎からグルチコイドが放出され、再び胸腺などリンパ系が萎縮、やがて副腎皮質の働きも低下し最終的には死亡してしまう。
この3つの期間をまとめて「全身適応症候群」という。
・リンパ系は異物を攻撃して排除する働きである免疫反応を引き起こす(異物とリンパ球との間に化学反応が起き、その生成物により周囲の血管がはれ上がり炎症が起きる)。ある種の遺物は体内に過激な免疫反応(アナフィラキシー)を起こしショック死してしまう。それを防ぐために副腎皮質からコルチコイドが分泌され胸腺などを萎縮させたと考えられる。そのため副腎皮質ホルモンは「抗炎症作用」があると考えられた。
一方ストレス反応経路は①脳下垂体から副腎皮質刺激ホルモンが放出されて起こるものと②自律神経の作用で起こるものの二つが考えられた。なお、自律神経の経路についてはセリエ存命中には解明されなかった。
①の場合
脳下垂体⇒副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)放出⇒副腎肥大⇒副腎皮質ホルモン(コルチコイド)放出⇒胸腺などリンパ系の萎縮
②の場合
自律神経⇒副腎髄質⇒アドレナリン⇒体細胞⇒粘液の分泌減少⇒消化酵素の作用に胃腸がさらされる⇒潰瘍や出血
・ロジャーギルマンにより視床下部と脳下垂体の間の血管に副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)が存在することが発見され。ストレス⇒視床下部⇒CRH⇒脳下垂体の経路が明らかになった。
【なぜ精神的ストレスが自律神経の失調を起こすのか】
・自律神経の仕組み
脳の活動とは無関係に状態により心臓の拍動をコントロールするなど、体内の状態を維持しようとする「ホメオスタシス」の機能により恒常性を保つ役割を自律神経が担っている。
ニューロンからニューロンへ電気信号(インパルス)が伝わり伝達物質(アドレナリン等)が放出される。交感神経と副交感神経により相互に協調し恒常性を保っているのである。
ストレスにより多量のインパルスが流れ込み自律神経の機能が失調されると考えられる。
【まとめ】
以上、セリエのストレス学説を概観してきたが、最後の自律神経機能の失調について、それは脳の興奮系の細胞が活性化されていると考えられている。本にも書かれていたが、脳には抑制系の機能を持った細胞も存在されているが解明されていないことが多い。マインドフルネス等瞑想などでは抑制系の脳が活性化され、心が落ち着き安定すると考えられる。
それは、大嶋信頼先生が強調されている無意識が働くことと近いのではないかと思う。現代催眠、FAP療法など無意識を活用する心理療法やマインドフルネス瞑想など、結果として抑制系の脳細胞が活性化する作用があることに取り組むことにより、脳の過活動による様々な生きづらさを軽減できるのではないかと、セリエのストレス学説をまとめながら改めて思いました。
もともとは、大嶋信頼先生の様々な著書のなかにホルモンや脳科学の言葉が出てくるので、より深く大嶋心理学を理解するために、セリエのストレス学説を理解して皆様と共有することは何か意味があるのではないかと思い。取り組みました。
結果、難しく読みにくい内容になってしまったかもしれませんが、大嶋先生もおっしゃっているように、「客観的な事実を淡々と観察しているうちに無意識が発動する」のであれば、限りがあるとはいえ、現代科学が明らかにした事実を学ぶのもまた、無意識が発動し無意識と一体になる一つの方法ではないでしょうか?
大嶋心理学→放送大学基礎医学→セリエのストレス学説(令和元年7月2日)
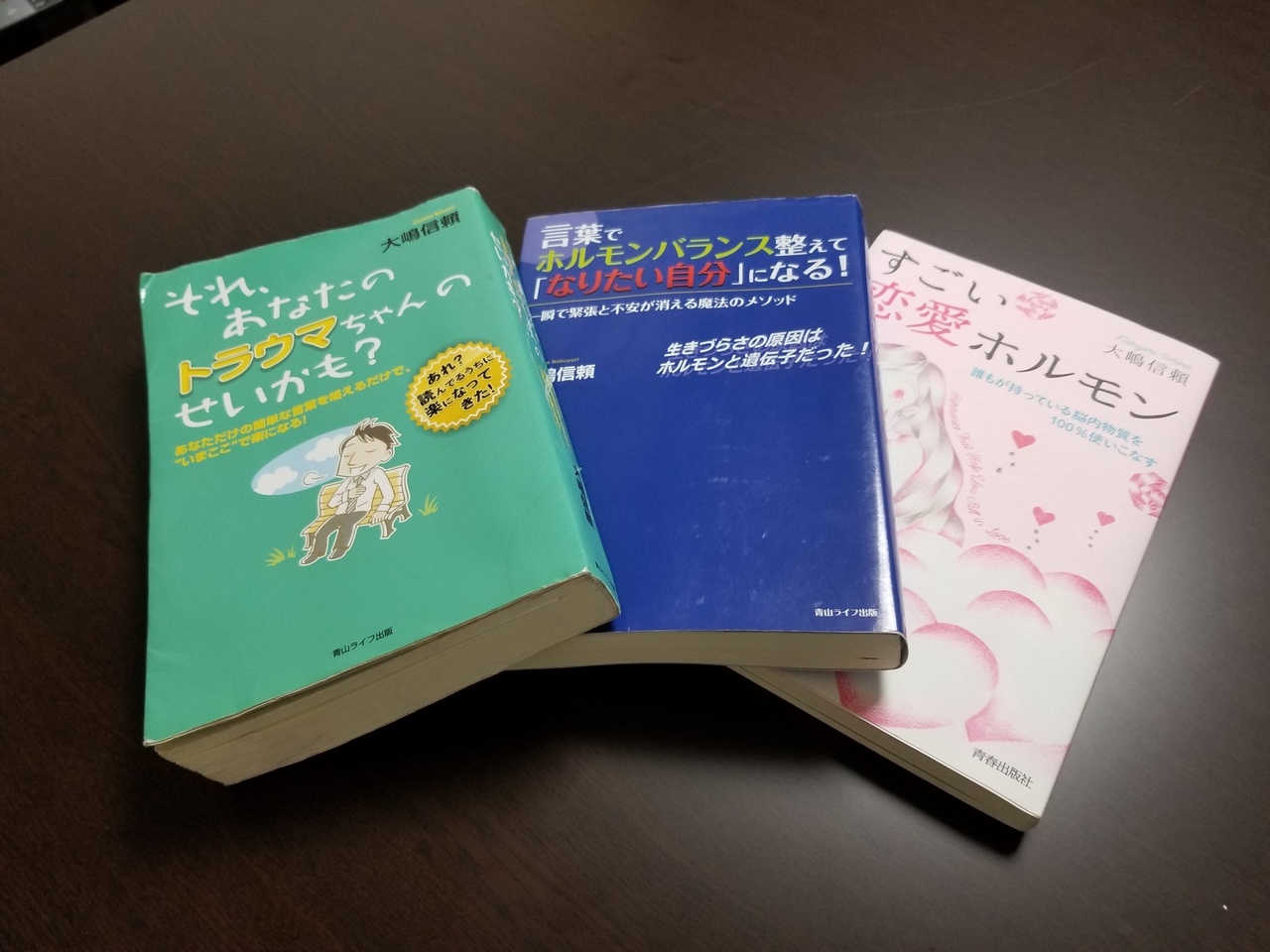
ホルモンを扱った大嶋先生の本。
大嶋信頼先生の<言葉でホルモンバランス整えて「なりたい自分」になる!>、<すごい恋愛ホルモン><それ、あなたのトラウマちゃんのせいかも?>の本を読み、トラウマ理解、人間理解には、ホルモン分泌など、人体の生体反応を体系的に理解した上で、精神医学・臨床心理学・カウンセリングを考える必要があると思い、放送大学に入学し、解剖学、病理学、生化学、運動生理学、睡眠学を学びはじめました。無駄のない講義なので、それぞれをしっかりと学ぶのも簡単ではないです。しかし、どの学問もそうですが、前半は基礎的な項目を学び後半に具体的な話、健康にどのように関係しているかという話になっている学問が多いように思います。
なので、前半は項目が並び、関係性が分からないので頭に入らない。しかし、後半に入ると応用になるので、前半の項目が再び登場、他の項目との関係がよく分かるようになります。しかし、やはり基礎的な科目なので、直接カウンセリングの話にはなりません(当たり前ですけどね)。
トラウマを治療すれば人生が開けてくるのではないか、少なくとも私はトラウマからの回復活動に取り組み人生が楽しくなってきました。回復活動は私の場合は単に、カウンセリングを受けるだけでなく、分子整合栄養医学で食事やサプリメントによる治療を受け、画像診断(ADHDなどの発達障害の本が出ています)で有名なダニエル・エイメンのメソッドをアメリカで学んできた医師のところに行き、Spect画像ををとり、脳のタイプを理解して対策を考える。ホルモンの検査、血糖値の5時間糖負荷検査および24時間検査を受け、食事の内容をさらに見直しました。おそらく現在できることはほとんど行っているのではないでしょうか、それはひとつひとつのことが意味がなかったということではなく、ひとつだけでは、完全ではないのでお互いを補完する関係で私の回復を支援してくれたと思っています。ある程度、専門家の意見も聞きますが、分野が多岐にわたるので私自身で必要なものをコーディネートしてきました。そこで役に立ったのが大嶋先生から教えてもらった「光に聴く」(大嶋先生の本では、「心に聴く」)が役に立ちました。様々な情報があるけど、自分に必要だろうか、迷うことが多くありましたが、すべて光に聴きその通りに選択してきました。結果は・・・いつわかるんだ?(笑)でも、光りに聴いた選択で後悔をしたことが一度もないのです。これは大きいかもしれないですね。自分の選択に後悔が無い人生というのは結構良いものですよ!
話が脱線しましたが、トラウマを治療するためにトラウマにより人のからだがどうなってしまうのか、PTSDの症状などはもちろん知っていますが、精神症状ではなくて、体がどうなってしまうのかそこの理解が必要。放送大学の科目ではトラウマを前提としていないので、もう少し核心に触れたくて、セリエのストレス学説を少し学びました。学生時代(若いときです)の心理学でももちろん学びましたが、今は放送大学の科目内容が頭に入っているので、書いてあることがよくわかる!。学生当時はホルモンのこととか自律神経のこととかよくわかっていなかったんですよね。
ということで、次回から、「ストレスとはなんだろう―医学を革新した「ストレス学説」はいかにして誕生したか」(杉 晴夫 著、講談社)にもとづき、セリエのストレス学説について、書きたいと思います。
日本トラウマティック・ストレス学会
(令和元年6月18日)
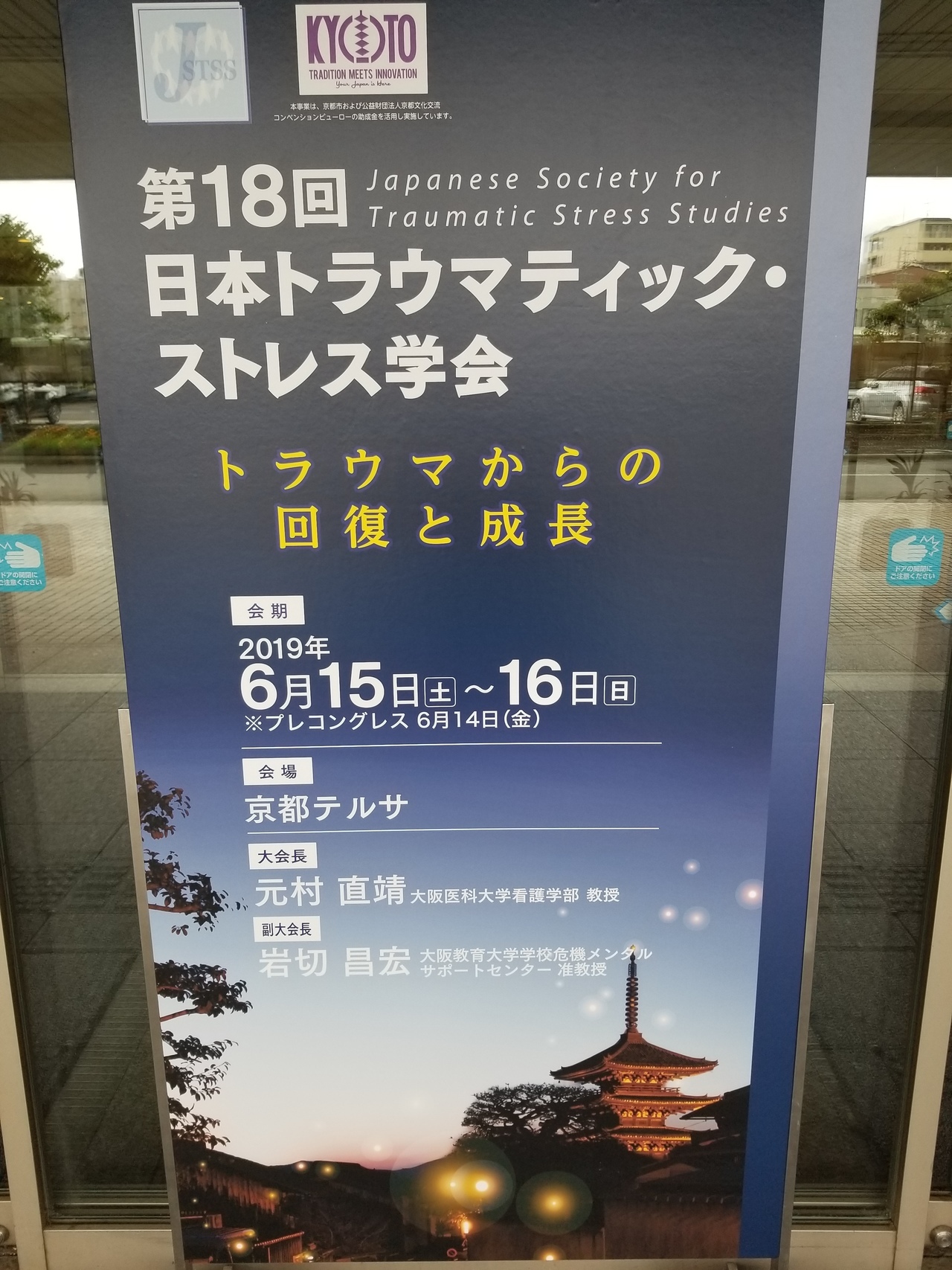
京都テルサにて開催

東本願寺
6月15日、16日に日本トラウマティック・ストレス学会に参加してきました。
全体を通して印象的だったのが、今まで病気をみて治療をしていた精神科医や心の問題をみて問題解決を図ってきた心理士の人たちが、個別でのトラウマ治療を突き詰めた結果。面接室内での治療だけではなく、人とのつながり、コミュニティ・社会とのつながり、コミュニティを一緒に作っていく過程の中で、回復していく。といった話が多かったように思います。
PTG(トラウマ後成長)やレジリエンスといったテーマの中でそのようなことが強調されていました。
それは、個人の中だけの問題ではなく、個人と環境との相互作用を促進していくという、ソーシャルワークの視点そのものだと思いました。
しかし、トラウマ治療ができるソーシャルワーカーがどれほどいるでしょうか、学会で発表してる先生方は医師や心理士が多いのですが、今まで社会福祉やソーシャルワークの教授先生方が、医療や治療の医学モデルに対して、生活モデルや社会モデルがソーシャルワークの専門性だと大きな声で主張していました。
しかし、学会では医師や心理士が「社会モデル」の中でトラウマ治療をしなくてはいけないと、声を上げています。その、講演や発表の中で、ソーシャルワーカー・社会福祉士・精神保健福祉士という言葉は聞こえてきませんでした。「社会モデル」のなかでのトラウマ治療にトラウマ治療を実施できないソーシャルワーカーが参加できるのでしょうか。
私が常々思っていることですが、ソーシャルワークの文脈の中で必要な時にはしっかりと医学モデルでのアプローチをソーシャルワーカーもできるようになるべきではないのでしょうか・・・。
少し愚痴めいた話にしてしまいましたが、少し学会で聴いてきた話をご紹介します。
基調講演では、「こどもの脳を傷つける親たち」(NHK出版新書)の著者である友田明美先生が「子ども虐待と脳科学」についてお話しされました。虐待の形態によって脳の変化する部位が違うことなど、虐待が脳に与える影響をわかりやすく説明してくださいました。
その中で、印象的だったのはドメスティック・バイオレンス(DV)の目撃は心理的虐待とされていますが、両親の「身体的な暴力によるDVの目撃」と「暴言によるDVの目撃」では脳に与える影響が「暴言によるDVの目撃」のほうがかなり大きく、またそれは、両親の学歴や貧困といった要因よりも大きな影響を与えるといった調査でした。
また、今までは主な虐待の加害者は母親が多かったのですが、父親が育児に参加するようになり、父親が主な加害者になっているケースが増えてきているとのことです。
また、FAP療法の「遺伝子の還元」を唱えるにも通じますが、虐待よって持ある遺伝子が発現してしまう。それが、トラウマによる様々な精神疾患に繋がっていく「エピジェネティクス」の話もありました。トラウマ治療で発現(ON)してしまった遺伝子を抑制(OFF)にできる可能性もお話しされていました。
この話を聞いてやはり大嶋先生の発想はすごいな、と少しづつ科学が大嶋先生の仮説を立証し始めていると思いました。
遺伝子に関しては他の先生の発表でも取り上げられており、トラウマの症状に起因する脳の部位を突き止め、特定の遺伝子に光を照射して、その遺伝子を抑制(OFF)にすると恐怖反応が消えるという実験結果がマウスで得られています。まだ基礎研究レベルで、応用するには様々なことを明らかにしていかないといけないが、遺伝子を抑制できる薬剤で新しいトラウマ治療も可能ではないかとの視座を提供してくれていました。
友田先生の話に戻り、昔に比べ、親が孤立して子育てをしてる環境が増えている。その中で体罰や怒鳴ることなく「ほめ育て」をすることが必要だと強調されていました。コミュニティのなかで、そのような環境を作らなければいけないことは明白です。
また、虐待などの厳しい逆境のなかで、回復成長していくには、そのような環境の中でもこの人はわかってくれる、理解してくれる、助けてくれるという存在を自分のなかに内在化していく必要があるとのことです。自分の中に頼れる人が居るといった感覚だと思います。
それは特定の人でなくても、宗教的な神や仏、宇宙との一体感、日本人で言えば神道でいう「八百万の神」でもいいとのことです。そこで、やはり大嶋先生の「心に聴く」とつながるのです。心に聴いて、その通り生きる。邪魔が入ったときには邪魔を排除してくださいと心にお願いする。単純でそんなので、人生何とかなるのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、この心との対話こそ、友田先生がお話ししてくれた「助けてくれる存在の内在化」でしょう。
心に聴くを日々実践するには、少し難しさもありますが、脳科学をトラウマ治療の観点から研究してきた友田先生も同じことを言っているのですから、大嶋先生の本に書いてある通り実践してみてはいかがでしょうか(リミットレスの本がわかりやすいと思います)。
学会での印象的な話と私の主な感想を書きましたが、何か特定のことだけではなく、一つ一つ必要なことを学び続けることが必要だということを改めて感じることが出来た有意義な学会でした。
次世代への現代催眠(令和元年5月31日)

加藤薫先生(右)と伊藤(左)
FAP療法開発開発者の大嶋信頼先生が師匠と仰ぐ故、吉本武志先生と一緒に臨床を行っていた加藤薫先生に会いに行ってきました。
吉本現代催眠の正統な後継者は加藤先生ではないでしょうか?
なにしろ、一緒に何十年も仕事をしていたわけですからね。講座を受けたとか、スーパービジョンを受けていたとは全然違うわけですね。先生は現在「引退」し、昔からのクライエントと以前からのつながりがある方から特別の依頼があったときのみ、講演・セミナーを引き受けているとのこと。心理療法より、禅などの実践から悟りの方に取り組んでいると笑ってお話されていました。
私の経緯を伝えたうえで(メール)、現代催眠とマインドフルネスについて教えを受けたいと事前に伝えていました。
始めに催眠に入れてもらいました。5分ほど催眠の体験ということでしたが。20分ほど、催眠に入れていただけました。
次に現代催眠について、加藤先生と吉本先生との出会いや、大嶋先生のFAP療法開発には吉本先生も関わっていたので、FAP療法誕生秘話から、吉本先生が現代催眠についてどのようにとらえていたかということまで、貴重なお話を、聞けました。
現代催眠について、明確な定義はなく、無意識(潜在意識)は我々の味方をしてくれるという前提にたった心理療法を指すとの事。
無意識なので、催眠のスキルは参考になるが、それだけでなく、例えば「絶対的な信頼」が生じる場面も無意識が働いているとのこと。
ロジャースにしても、各流派を突き詰めるとそこには無意識の力が働き。トランス状態が生まれているのではないか、と加藤先生のお話を聞きながら私は想いました。
私の一番の目的は、目の前の人と裁くことなく関わるには、現代催眠を身に付ける必要があるのではないか、ということでしてた。
加藤先生からは、伊藤さんが考える裁かない関わりとは何か?とあったので、私は「その人が正しいとか間違っているとか、そうすべきとか、するべきではないとか、ということを、とりあえず置いて置くこと」と答えました。
それに対して、加藤先生は、それは間違っていないし。それ以上の答えはないのてはないか、伊藤さんはすでに、裁かない関わりが、出来ているのではないかと。言っていただきました。
私から、そう思っていても、解決を焦る自分がいるのです。と伝えると「なるほどねー」という感じでした。
FAP療法で回復してきた自分を、感じている一方、FAP療法が本当に効果があるのか、疑っている自分がいることも伝えました。
FAP療法について、吉本先生も関わっているが、しかし、FAP療法を、取り入れることはなかった。バージョンアップしていくFAPについても、今、吉本先生が、生きていても何も言わなかっただろうとの事。そこには、否定も肯定もないようであった。
吉本先生は、最終的には何かの形を持たず、自然体でクライアントと向き合い、何故か知らないうちに。クライアントが、よくなっていくそんな臨床をしていた。加藤先生も様々な研修セミナーを受けてきたが、そのような形になっているとの事。しかし、場合によっては古典催眠を施してみたり、クライアントの希望に、純粋に答えてみたりと、柔軟な対応をしているようだった。
その上て、伊藤は若いので、FAPを始め、今勉強をしていることをしっかりと自分のものにして、伊藤オリジナルのスタイルを。つくってほしいと、伝えてくれた。
そうなんです。現代催眠だろうが、FAPだろうが。ソーシャルワークだろうが何でもいいんです。
苦しんでいる人が、苦しみ続けることなく、なんとかでもその人らしい、生き方が出来るような社会になれば、その方法論は、何でもいいんです。
ただ、その方法がその人にしか出来ない方法であっては困るので、学問・科学としての理論を次の世代に残せるものを私は選択したい。
専門職の覚悟!(令和元年5月17日)
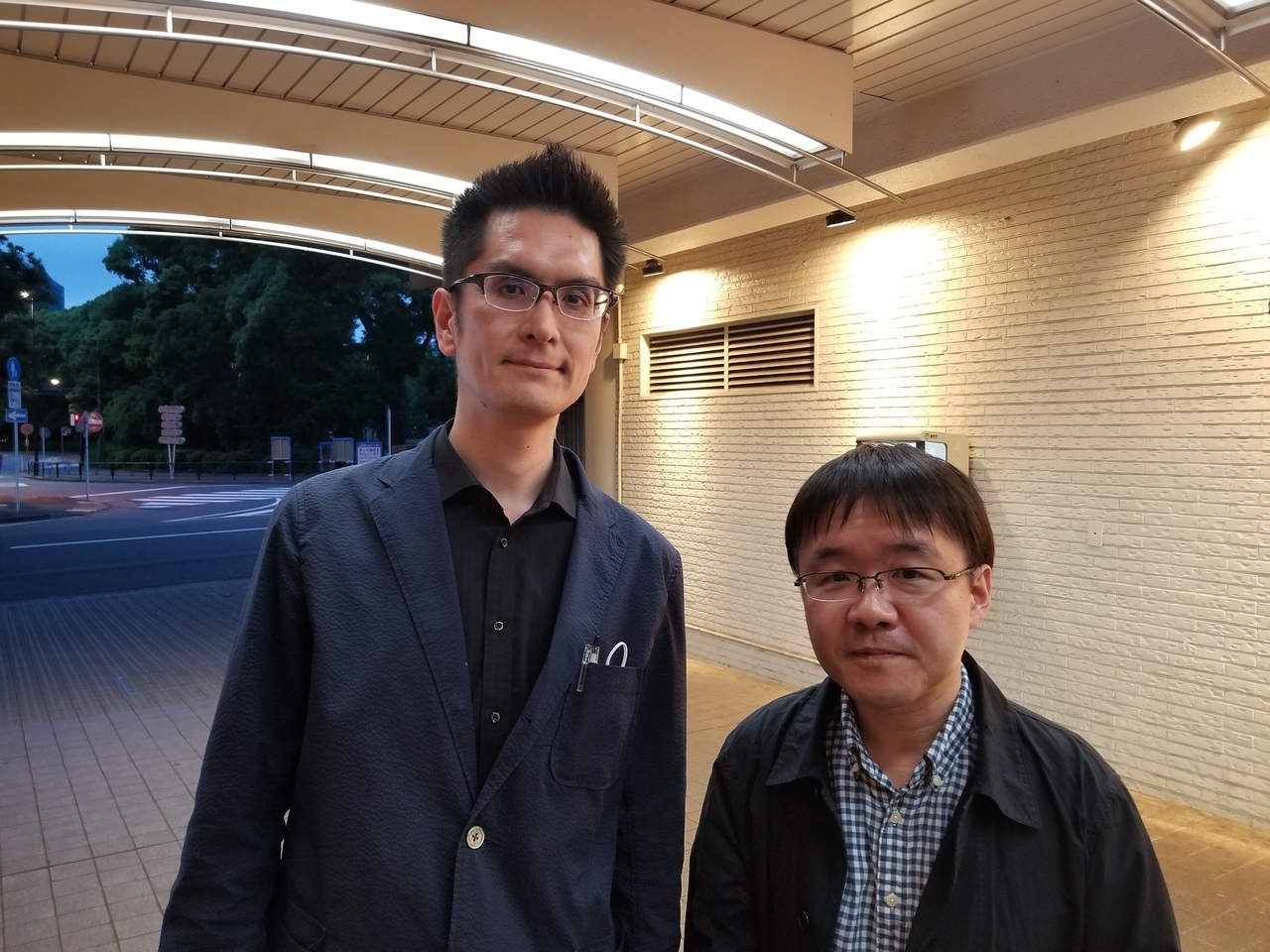
関内カウンセリングオフィスの田中究先生(右)伊藤(左)
5月12日に関内カウンセリングオフィス「システムズアプローチステップアップ研修」と「慶應義塾大学病院精神・神経科家族療法システムズアプローチ勉強会」との共催で行われた研修に参加してきました!
関内カウンセリングオフィスの研修はもう参加して3年を過ぎました。慶応義塾大学の勉強会には今後参加させていただく予定です。
両講座の講師を務める田中究先生は、ブリーフサイコセラピー学会理事であり、家族療法学会認定のスーパーバイザーです。
言葉が混乱しますので、このコラムではシステムアプローチ=家族療法=ブリーフセラピーとして扱います。この辺の用語の整理は後日ホームページに掲載したいと思っています。
数年前からブリーフセラピーの勉強を始めたのですが、一つの流派である「ソリューションフォーカストアプローチ」から学びました。しかし、技法中心でそれだけで様々なクライエントに対応できると思えず、システム論的に物事をとらえるブリーフセラピーの研修も受けていました。しかし、私がバカだったのでしょうか、用語の説明が分かっても、それと実践とが結びつかず、「分からない!」となってしまいました。
しかし、諦めたくなく関内カウンセリングオフィスのシステムズアプローチ研修会に参加しました。
そこで、田中先生の講義とワークが私の中で結びつき、用語と実践が結びつくようになりました。まあ、それと「出来る」とは違うのですが、研修を受けてからの私の面接は大きく変わったように思います。「分からない」が「分かった」に変わったのは何よりも大きなことでした。
講座の中で講師の田中先生と同オフィスの安江先生からは、システムズアプローチは「ものの見方」なのだと繰り返し説明がありました。クライエント・家族の状況をどのように見るかはもちろん、カウンセリング場面のなかで、カウンセラーも含めて、どのようなコミュニケーションの相互作用が起こり、どのような関係性になっているのか、ということに着目するためのトレーニングなのだと私はとらえています。
なので、そこで他の療法・アプローチがなされていてもシステムズアプローチを適用できるのです。
そこで何が起こっているのかが分かれば、次に何をすればよいかが分かる、という訳です。これは、様々な場面で自分自身の振りかえりに活用することが出来ました。また、カウンセリング場面のなかで自分の面接を客観視することが出来るようになってきました。
しかし、システムズアプローチはセラピーでもあるので、治療的な関り方も提供してくれます。ここでいう治療とは、問題を作っている硬直化した状況に変化を起こすことだと私は捉えています。
その方法としては、クライエントに合わせることと、クライエントの枠組みをはずす(変化を起こす)ことだと繰り返し研修の中で強調され、受講者は合わせること(ジョイニング、チューニング、ミラーリングなど教える人によって呼び方は様々です)とはずすこと(リフレーミング)をすることに四苦八苦しながら取り組みます。講師の講義とワーク、そして指導を受けながらロールプレイに繰り返し取り組んでいます。
もう一つ、この研修会の私が気に入っているところは、多職種が参加しているところです。心理職だけでなく。医師・看護師・ケアマネージャー・ソーシャルワーカーなど支援にかかわる多くのひとが参加しています。
私がIAPで目指している専門職の統合には、共通言語を持つことがまず必要ではないかと思っています。なので、この研修会の在り方が一つのモデルとしてとても参考になります。
以上のように継続的にシステムズアプローチの研修に参加してきました。そして、今回の慶応義塾大学神経精神科の方々との研修に至ります。
システムズアプローチのロールモデルを一度しっかりと見て理解することを目的に、家族療法・システムズアプローチの第一人者である吉川悟先生によるロールプレイの面接をDVDで鑑賞しました。そのなかで何が起こっているのかを田中先生が解説し、参加者同士で議論していくという内容でした。
解説・議論の内容は多岐に及びますが、私が印象的だったのは、クライエントである夫婦が吉川先生のもとにたどり着くまでに2名の専門職との面談を経ているという設定の中、これまでに相談した専門職から「家族調整が必要だ」と言われてきたと伝えても、吉川先生は「関係がない」「家族関係には問題がない」と言い切り、どのようにして解決していくか一緒に考えていくという姿勢でした。
それは、それまでの専門職を否定しているわけではなく、様々な狙いのもと行っているわけですが、今、目の前にいるクライエント・家族にとって一番必要としていることは何か、ということを最優先している吉川先生の「覚悟」を私は感じました。
今までの専門職が言っていることを「関係ない」と言い切ってまで、今、必要なことを行うという、まさに「クライエントファースト」の実践だと思いました。
様々な組織の中でソーシャルワークを実践してきた私は、様々な人や組織の板挟みになってしまい、常に「クライエントファースト」の実践が出来ていたかというと、反省しないといけない場面がいくつかあります。
私が独立したのも組織のしがらみからから放たれ、まず、目の前のクライエントの利益を優先することに100%力を注ぎたかったからです。しかし、一番必要なことは、どのような組織・社会の制約に縛られていても、その中でクライエントの利益を引き出すことを最優先する実践だと思います。
私がやらなくてはいけないことは、まだまだたくさんあります。いろいろいろなことに手を出しすぎているのではないか、と自分でも思ったり、周りから忠告されたりもします。しかし、すべてが必要なものなのです。優先順位をつけてこなしていきたいと思います。
以上、システムズアプローチ研修の体験談でした。「覚悟」がキーワードだったように思います。
P・S システムズアプローチはオープンダイアローグの土台になっており、また、FAP療法もブリーフセラピーの延長線上に大嶋信頼先生が開発したものです。すべてがつながっています。その辺りのつながりに関しても、いつか分かりやすく書きたいと思います。そのために一つ一つしっかりと掘り下げて学んでいきたいと思っています。

